

【除湿と送風】それぞれの役割と使い分けを知り、湿気と電気代を解決しよう
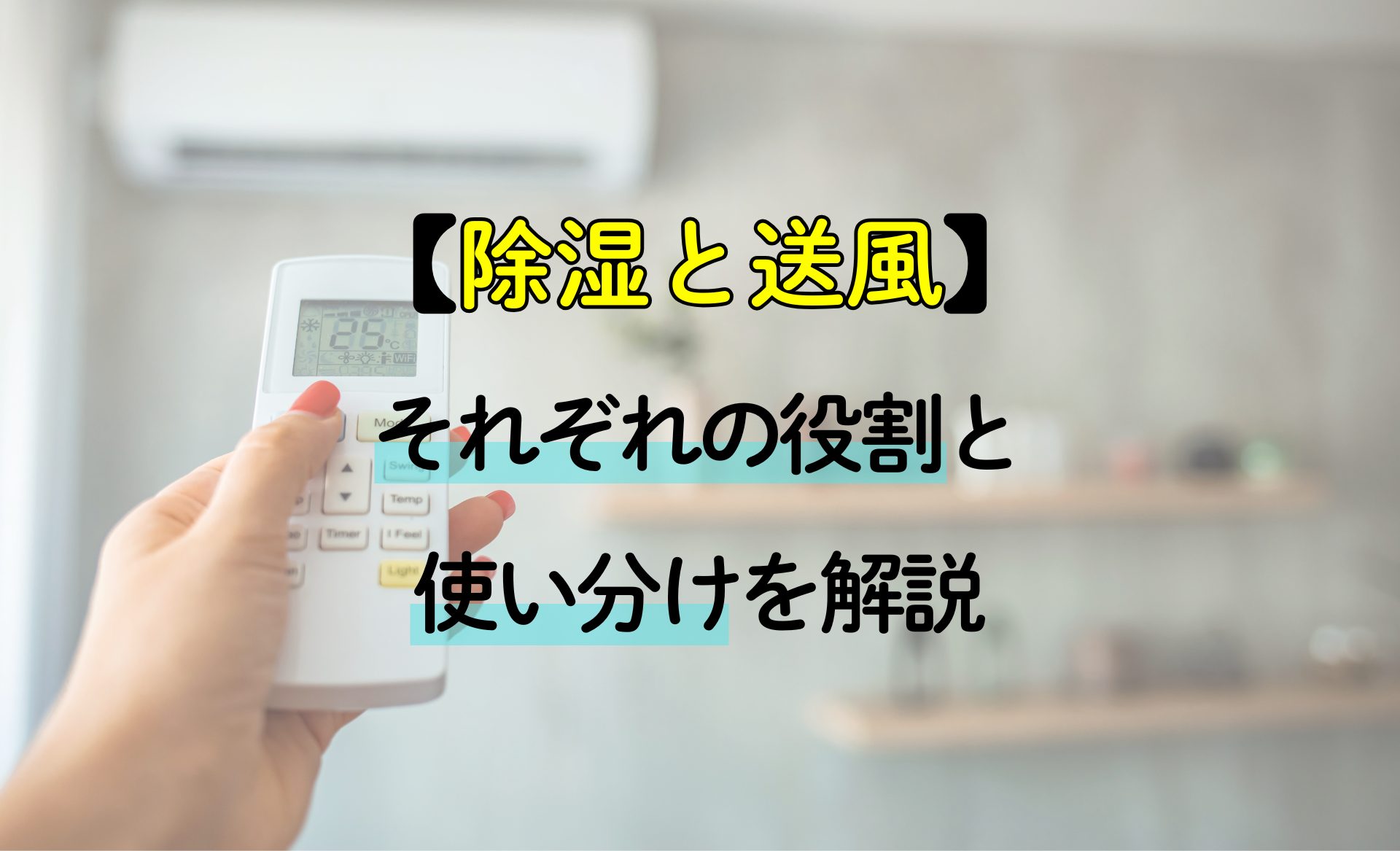
「エアコンの除湿機能と送風機能って、どう違うの?」
「機能の違いは分かるけど、具体的にどう使い分けていいのか分からない」
「送風も除湿効果があるの?」
と、除湿機能と送風機能の使い分けにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実際、それぞれの用途はまったく異なり、正しく使えていない場合は期待している効果が得られない可能性や、電気代が必要以上にかかってしまう場合があります。
適切にエアコンを使用するために、本記事では、以下の点を解説します。
- エアコンの除湿と送風の違い
- 除湿機能の使用がおすすめなとき
- 送風機能の使用がおすすめなとき
- 除湿を使うときの注意点
- 送風を使うときの注意点
- 送風がないときの解決策
- 除湿と送風の代用アイテム
それぞれの機能の正しい役割を知り、快適な生活空間を保てるように工夫しましょう。
エアコンの除湿と送風の違い
エアコンの除湿機能は、湿気が高くやや暑さが気になる時期に使用する機能です。
室内の湿気を取り除き、新しい空気を送り出します。その際に、冷却された空気を吐き出すため、湿度と温度の両方を解決してくれます。
一方で送風機能は、室温を一定に保ちたいときに使用。風を送ることで室内の空気を循環させ、部屋全体の空気の温度を一定にします。
室温を下げる役割自体は担っていませんが、エアコンから送られてくる微風により清涼感を得られます。
送風の消費電力は冷房や除湿と比べて低いため、少し涼みたいときに使用すると光熱費が節約できます。
| 除湿 | 送風 | |
| 冷房効果 | 〇 | △ |
| 除湿効果 | ◎ | △ |
| 室温を一定に保つ効果 | △ | ◎ |
| 消費電力 | 〇 | ◎ |
除湿機能の使用がおすすめなとき
この章では、エアコンの除湿機能の使用をおすすめする、具体的なケースを3つ紹介します。
- 蒸し暑いとき
- 部屋干しをするとき
- 湿度を下げたいとき
【おすすめ1】蒸し暑いとき
梅雨や夏場、気温はそれほど高くないのに「なんだか不快」と感じることもありますよね。
その理由は、空気中の湿度の高さです。
湿度が高いと体感温度が上がり、べたつきや汗の乾きにくさから不快感が増します。
この場合、除湿を使って、不快感の原因である湿度を下げるようにしましょう。
湿気を取り除くだけで体感温度が下がり、肌に触れる空気もさらっと快適になります。
【おすすめ2】部屋干しをするとき
雨の日や、花粉や黄砂が多い季節には、洗濯物を部屋干しするご家庭も多いでしょう。
しかし、部屋干しはどうしても湿度が上がり、なかなか乾かない、臭いが気になるという悩みがつきものです。
そんなときは、エアコンの除湿機能が大活躍します。
洗濯物の水分を効率よく取り除き、乾燥時間が短くなる傾向にあります。
そのため、雑菌の発生や繁殖が抑えられ、生乾き臭の予防にもつながります。
【おすすめ3】湿度を下げたいとき
多湿の環境では、蒸し蒸しとした不快感があるだけではなく、カビやダニの発生率を高めてしまいます。
人が快適に暮らせる環境は湿度40%から60%ほど。この範囲を超えるとカビやダニが発生しやすくなります。
特に梅雨時期や秋雨の時期は、室内の湿度が60%を超えることも少なくありません。
湿度を60%以下に保つことで、カビやダニの繁殖を防ぐ効果があります。
普段から除湿を活用して、快適かつ清潔な空間を保ちましょう。
送風機能の使用がおすすめなとき
この章では、エアコンの送風機能の使用をおすすめする、具体的なケースを3つ紹介します。
- 少しだけ涼みたいとき
- 冷房時の電気代を抑えたいとき
- エアコンのカビ予防をしたいとき
【おすすめ1】少しだけ涼みたいとき
「エアコンの冷房を入れるほどでもないけど、ちょっと暑いな」と感じるときもあるでしょう。その際は、送風を使ってみてください。
送風は室温を下げるための機能ではありません。しかし、風が肌に当たることで涼しく感じます。
また、汗を蒸発させる効果も期待できるため、帰宅後の少し汗ばんでいるときにもいいでしょう。
冷房のように冷えすぎる心配がないので、小さなお子さんがいるご家庭でも安心です。
【おすすめ2】冷房時の電気代を抑えたいとき
室内が暑いときに冷房をつけると、室温を下げるために普段より多くの電力を消費します。
これによって、電気代が高くなる可能性があります。
電気代を抑えながら冷房で室温を下げたいときは、まず送風モードで部屋の熱気を逃がしておきましょう。
このあとに冷房を使うことで、より少ない消費電力で室温を下げることができ、また、必要以上に設定温度を下げる必要もありません。
【おすすめ3】エアコンのカビ予防をしたいとき
エアコン内部は、湿度が高い状態が続くとカビが繁殖しやすくなります。
冷房や除湿を使った後に送風モードで乾燥させ、カビの繁殖を防ぎましょう。
しかし、送風機能そのものは、カビの発生を抑えるためのものではありません。
カビのエサとなるほこりが溜まっていたり、長期間エアコンを使っていない場合は、カビが繁殖している場合があります。
そのときに送風をすると、風と一緒にカビの胞子が部屋中にばら撒かれてしまいます。
定期的な手入れは、欠かさないことが重要です。
除湿を使うときの注意点
除湿は非常に便利な機能ですが、設定温度や使い方によっては不快感や電気代の高騰につながる可能性があります。
除湿の次の3つの特徴をおさえておきましょう。
- 冷えすぎることがある
- 電気代がかかる場合がある
- 梅雨と夏以外の時期には不向き
【注意点1】冷えすぎることがある
除湿の主な目的は湿度を下げることであり、冷房に比べると室温を下げる効果は低いです。
しかし、設定温度や風向きによっては、部屋が冷えすぎることがあります。
また、夏場は外気温との差で、体調を崩す可能性もあります。
除湿を使用する際は、以下の設定がおすすめです。
- 風向き: 水平もしくは上向き
- 設定温度: 26度~28度
【注意点2】電気代がかかる場合がある
除湿機能は、冷房機能より消費電力が低いと思っている方も多いでしょう。
確かに、同じ設定温度で使用したときの消費電力は除湿の方が低く、そのため電気代も抑えられます。
しかし、湿気があまり気にならないときや、真夏のように外気温が高いときは、冷房のほうが電気代が安くなる可能性があります。
なぜなら、室温の冷却を主な目的としていない除湿で、冷房と同等の効果を得ようとすると、設定温度を必要以上に下げなくてはいけないからです。
これにより、除湿でも電気代がかかってしまう可能性があります。
冷房と除湿の使い分けは、以下の3つを意識してください。
- 湿度が気になる日: 除湿
- 暑さが気になる日: 冷房
- 湿度と暑さの両方が気になる日: 自動運転、もしくは冷房で室温を下げてから除湿に切り替え
【注意点3】梅雨と夏以外の使用は不向き
除湿は湿度を下げるだけではなく、室温も下げてしまいます。
そのため、春秋のような涼しい季節や、冬のような寒い季節の使用は不向きです。
除湿を通年行いたい場合は、除湿機や湿気取り剤など、湿気取りに特化した電化製品やアイテムがおすすめです。
送風を使うときの注意点
送風は電気代が安く、空気の循環にも役立つ便利な機能です。
しかし、用途を誤解したまま使うと、期待している効果が得られないかもしれません。
以下3つの点に注意しながら、送風を使うようにしましょう。
- フィルターの掃除は必要
- 電気代がかかる可能性がある
- 換気機能はない
【注意点1】フィルターの掃除は必要
送風機能は、カビ対策になることでも知られています。
しかし、フィルターに溜まったほこりやカビを取り除く効果はなし。汚れが溜まっている場合は、送風の使用だけでカビを予防することはできません。
送風機能はエアコン内部の空気を循環させるため、フィルターの汚れがそのまま部屋に拡散されるリスクがあります。
エアコンのフィルターは、2週間に1回程度を目安にこまめに掃除しましょう。
異臭がする場合は、すでにカビが発生している可能性もあるので、できるだけ早めに掃除するようにしましょう。
【注意点2】電気代がかかる場合がある
送風は他のモードに比べれば省エネですが、一日中つけっぱなしにしていると、電気代がかさみます。
また、室内の除湿や冷房を主な目的にした機能ではありません。
そのため、部屋干しの生乾き予防や夏場の室温改善のために送風を使っても、電気代の無駄といえるでしょう。
【注意点3】換気機能はない
送風は、機械内から空気が送られてくるため、換気につながると考える方もいるかもしれません。
しかし、送風の目的は空気の循環です。
室内の空気を循環させて、一か所に熱気や湿気が留まることを予防する効果は期待できますが、新鮮な外気を取り込めるわけではありません。
高温多湿が気になる場合は除湿や冷房を使いましょう。
生活臭が気になるときは、消臭剤や窓を開けての換気がおすすめです。
送風がないときの解決策
古いタイプのエアコンや簡易モデルでは送風機能が搭載されていない場合があります。
そのときは、室温より高い温度で冷房を設定してみましょう。
実質的には空気だけが送られてくるような、送風と同じ効果が得やすいです。
湿気とカビを防止する、除湿と送風の代用アイテム
除湿・送風だけでは不十分なときや、エアコンを使うほどでもないときもありますよね。
そんなときは、以下5つのような代用アイテムを取り入れてみてください。
より快適で清潔な室内環境を保つことができます。
- 除湿機
- 扇風機
- サーキュレーター
- 空気洗浄機
- 湿気取り剤・調湿剤
【アイテム1】除湿機
除湿器は、湿気を取り除くことに特化している製品です。
エアコンの除湿機能のような空気の冷却機能はありませんが、ジメジメ感の緩和やカビ対策が効率的になります。
除湿には効果的ですが、一方で電気代がかかるデメリットがあります。
節約をしたい方は、電化製品以外の湿気対策も検討してみてください。
【アイテム2】扇風機
他のアイテムで除湿をしながら、涼を得たいときにおすすめしたいのが、扇風機です。
室温を下げる効果はありませんが、風を送ることで涼しさを感じることができます。
また、部屋干しをしているときは、風が洗濯物に直接当たるように置くこともおすすめ。
風で洋服の水分が飛ばされ、効率的に乾かすことができます。
エアコン除湿では、十分に部屋が涼しくならないとお悩みの方は、扇風機を活用してみてください。
【アイテム3】サーキュレーター
サーキュレーターは、エアコンの送風と同じく、室内の空気を循環させることができます。
そのため、室内の室温や温度を一定に保ちたいときにおすすめ。
また、サーキュレーターの風を部屋干ししている洗濯物に当てることで、生乾きを防ぎやすくなります。
部屋干しをする際の湿度の高さや生乾き臭が気になる方は、活用してみてください。
【アイテム4】空気洗浄機
空気洗浄機の中には、除湿機能を兼ね備えている製品も多くあります。
除湿機と異なる点は、空気中のホコリや花粉、PM2.5なども除去できること。
カビの発生を予防しながら、身体に害のある物質を除去できるため、清潔かつ安心感のある室内環境を整えることができます。
湿気だけではなく、お子さんの喘息などの不安もある方は、除湿機能付きの空気洗浄機を購入しておくことで、場所も節約できるでしょう。
【アイテム5】湿気取り剤
できるだけお金や手間をかけずに湿気対策をしたい方には、湿気取り剤がおすすめです。
湿気取り剤とは、置くだけで湿気を吸収してくれるアイテムのこと。
湿気取り剤のなかには、半永久的に使用できるため買い替えが不要な商品もあります。
そのため、かかる費用は購入時のみ。電気代や買い替えにかかる費用を気にしなくていい点がうれしいポイント。
小型のものであれば、靴箱やクローゼットなど、エアコンの機能が届きにくい場所の湿気対策も可能です。
こうした場所は、密閉されており湿気も溜まりやすいため、カビにとっては好都合な菅子湯です。
湿気取り剤を使って普段から除湿をするようにしましょう。
室内の除湿をするなら、炭八がおすすめ!
できるだけ出費を抑えながら、常に室内の除湿を行いたい場合は、調湿剤の炭八がおすすめです。
炭八の特徴は、針葉樹を原料としていること。その吸湿力は備長炭の約2倍です。
さらに、半永久的に使用できるため買い替える必要がありません。
使い方はとてもシンプルで、湿気が気になる箇所に置いて放置しておくだけ。
靴箱用やクローゼット用の小さなサイズの商品もあるため、除湿機やサーキュレーターなど、電化製品が使いづらい場所でも活躍します。
吸湿力が下がったと感じたときは、天気がいい日に天日干しをするだけで大丈夫。
炭のなかに溜まった湿気を吐き出し、吸湿力を取り戻してくれます。
まとめ
本記事では、エアコンの除湿機能と送風機能を正しく使えるよう、以下の項目をお伝えしました。
- エアコンの除湿と送風の違い
- 除湿の使用がおすすめなケース
- 送風の使用がおすすめなケース
- 除湿を使うときの注意点
- 送風を使うときの注意点
- 送風がないときの解決策
- 除湿と送風の代用アイテム
それぞれの機能を正しく使うことで、室内を快適に保てるだけでなく、電気代も抑えられます。
もしエアコンの機能だけで十分な効果が期待できない場合は、代用アイテムも活用してみてください。
著者情報
最新の投稿
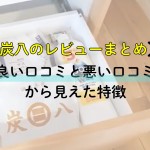 炭八2026年2月11日炭八のレビューまとめ|良い口コミと悪い口コミから見えた特徴
炭八2026年2月11日炭八のレビューまとめ|良い口コミと悪い口コミから見えた特徴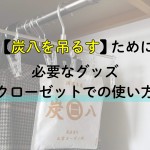 炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説
炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説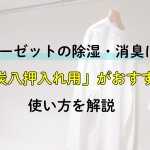 炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説
炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説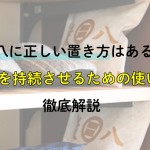 炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説
炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説




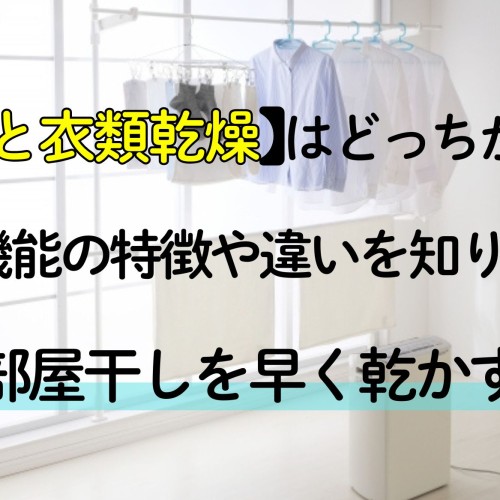
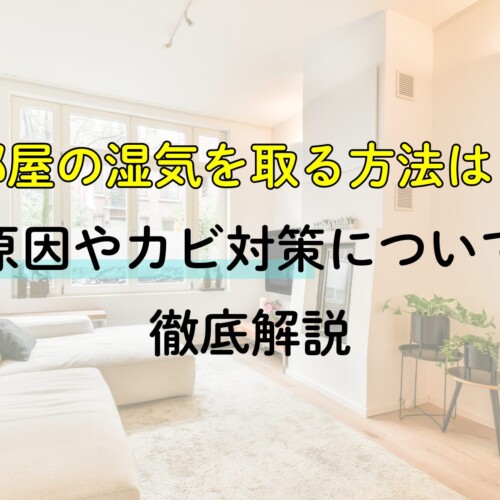
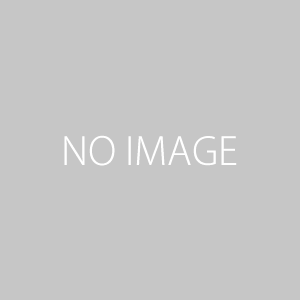

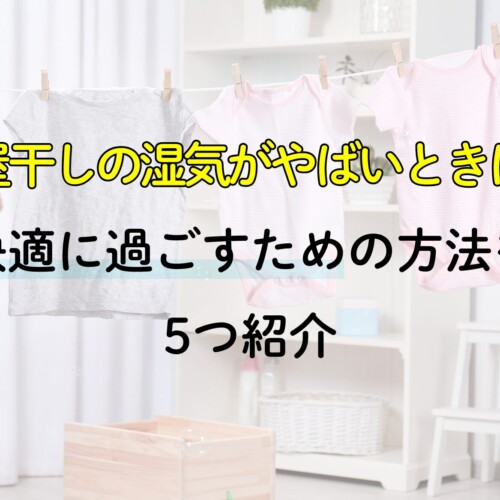


この記事へのコメントはありません。