押入れのカビがひどい!安全な掃除方法・ひどくなった原因と対策
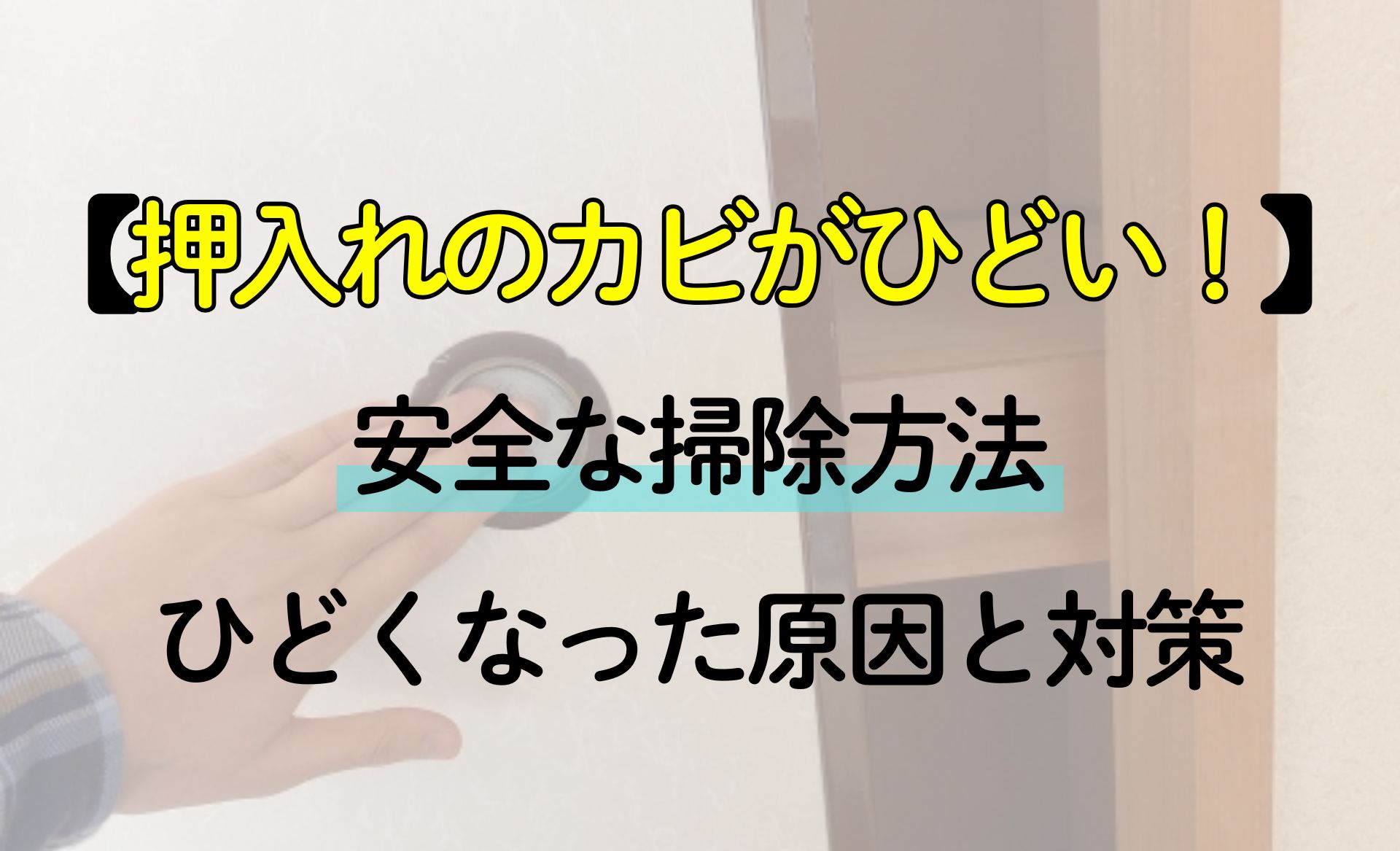
押入れは湿気がこもりやすく、普段あまり開け閉めしない場所だからこそ、気づかないうちに押入れのカビがひどくなったことはありませんか?
「漂白剤を使えばきれいになるよね」「とりあえず拭き取れば大丈夫」といった間違った対処法では、かえって状況を悪化させたり、健康被害を引き起こしたりする危険性があります。
今回は、押入れのカビがひどいときの対処法について、以下のポイントを解説します。
- 押入れのカビがひどいときの除去方法
- 押入れのカビがひどくなった原因
- 押入れのカビをひどくさせない対策法
家族の健康と大切な荷物を守るために、カビ対策の正しい知識を身につけましょう。

押入れのカビがひどいときの掃除方法

押入れに発生するカビは、おもに白カビ・黒カビ・緑カビの3種類です。
それぞれカビの種類によって、特徴・落としやすさ・適した除去方法があります。
| カビの種類 | 白カビ | 黒カビ | 緑カビ |
| 特徴 | ・白色 ・ふわふわで綿のような見た目 ・アレルギーの原因になることも | ・黒色 ・ポツポツした見た目 ・木材などに根を張り奥まで入り込む | ・木材に発生しやすい ・木材を腐らせる |
| 発生条件 | ・湿度60~80% ・温度20~30℃ | ・湿度70%以上 ・温度25~30℃ | ・湿度60%以上 ・温度25~35℃ |
| 落としやすさ | 〇 | ✕ | △ |
| 対処法 | エタノール | 次亜塩素酸・塩素系漂白剤 | 次亜塩素酸・塩素系漂白剤 |
押入れのカビを掃除するときは、作業を安全で効果的に進めるために、以下の準備を行いましょう。
- 押入れの中に入っているものをすべて取り出す
- 窓や扉を開けて空気の通り道を確保する
- マスクを着用してカビの胞子を吸い込まないようにする
白カビの掃除はエタノールで
表面にふわっと広がる白カビには、エタノールが有効です。
文部科学省の調査によれば、アルコール濃度70〜80%のときに最も強い殺菌力を発揮することがわかっています。
白カビの除去にはアルコール濃度70~95%の「消毒用エタノール」を使うのが適しています。
準備するもの
- 消毒用エタノール
- 雑巾
- ゴム手袋
カビを取る手順
1.ゴム手袋を装着する
2.濡らして固く絞った雑巾で、ほこりなどを取り除く
3.消毒用エタノールを吹きかける。カビが発生していない場所にも押入れ全体的に吹きかける
4.十分に乾燥させる
黒カビ・緑カビには次亜塩素酸水を
根を張り奥まで入り込む黒カビには、次亜塩素酸水で除去しましょう。
ここで使うのは、塩素系漂白剤の成分である次亜塩素酸ナトリウムではなく、「次亜塩素酸水」です。
消臭効果が高く、ノロウイルスに効果がある次亜塩素酸水ですが、ドラッグストアなどで購入できますよ。
粉末の次亜塩素酸水は、400ppmに薄めて使用しましょう。
準備するもの
- 次亜塩素酸水
- 雑巾
- ゴム手袋
カビを取る手順
1.ゴム手袋を装着する
2.濡らして固く絞った雑巾で、ほこりなどを取り除く
3.次亜塩素酸水を吹きかける。カビが発生していない場所にも押入れ全体的に吹きかける
4.黒カビが落ちるまで放置する
5.固く絞った雑巾で拭く
6.十分に乾燥させる
それでも落ちないカビは塩素系漂白剤で
黒カビや緑カビは根を深く張るため、次亜塩素酸水だけでは完全に落とせない場合があります。
どうしても落ちないカビには、市販のカビ取り剤として販売されている「塩素系漂白剤」を使用しましょう。
塩素系漂白剤は強いアルカリ性のため、木材の色落ちや劣化を招く可能性があります。
賃貸物件や色の変化が気になる箇所では使用を避けましょう。
準備するもの
- 塩素系漂白剤
- キッチンペーパー
- ラップ
- ゴム手袋
- 必要に応じてメガネやゴーグル
カビを取る手順
1.保護のためゴム手袋やメガネ・ゴーグルを装着する
2.キッチンペーパーに塩素系漂白剤を含ませる
3.カビが気になる部分に塩素系漂白剤を含ませたペーパーを置き、ラップで覆う
4.10分ほど放置する
5.貼り付けたキッチンペーパーをはがす
6.水を含ませたキッチンペーパーで塩素系漂白剤をしっかり拭き取る
7.十分に乾燥させる
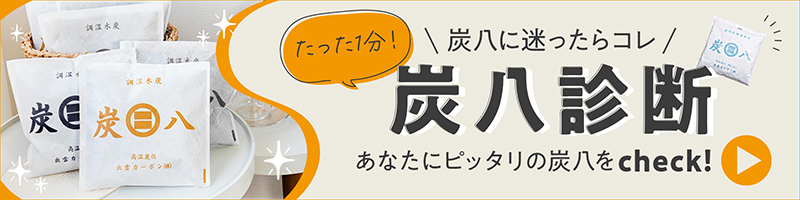
押入れのカビがひどくなった原因

押入れのカビを除去しても、根本的な対策を講じなければカビが再び繁殖し、より深刻な状況になってしまいます。
なぜ押入れのカビがひどくなったのか、原因を知ることが大切です。
カビが生える条件
- 温度:25℃。5~35℃でも繁殖します
- 湿度:65%以上
- 栄養:皮脂汚れ・ほこり・食べこぼしなど
カビは、温度・湿度・栄養の3つの条件がそろうと繁殖します。
カビは温度・湿度・栄養の3つのうち、どれか1つでも欠けていると繁殖しません。
「普段から押入れまで気を配れない…」という方も少なくないでしょうが、簡単な対策を心がけるだけでカビを予防できますよ!

押入れのカビをひどくさせない!対策法

以下の対処法をとれば、押入れにカビが繁殖することなく、清潔で快適な収納環境を維持できます。
- 押入れの空気を入れ替える
- 押入れの収納に余白を作る
- こまめに掃除する
- 十分に乾かしてから収納する
- 炭八を置く
対処法①押入れの空気を入れ替える
カビが繁殖する3つの条件「湿度・温度・栄養」のうち、換気は湿度をコントロールする最も効果的で基本的な対策です。
カビは湿度65%以上で活発に繁殖します。
押入れは密閉空間のため湿気がこもりやすく、湿気が上がりやすい環境です。
換気によって湿った空気を外に出し、乾燥した新鮮な空気を取り入れれば、湿度を効果的に下げられます。
- 定期的に換気をする
- 晴れた日がおすすめ(部屋の湿度が低いことが多いため)
- ふすまは片方だけでなく、両サイドを開け、空気を通りやすくする
- エアコン・扇風機・サーキュレーターを活用し、押入れに空気を送る
対処法②押入れの収納に余白を作る
押入れは詰め込みすぎないようにし、すき間を作りましょう。
押入れに物を詰め込みすぎると空気の通り道がなくなり、湿気が停滞してしまうからです。
隙間があることで空気が循環し、湿った空気が外に出て、乾燥した空気が入ってくる流れを作れます。収納するときは、押入れの70~80%程度の量にとどめるようにしましょう。
また、隙間があれば押入れの奥まで目が届きやすくなり、掃除機などで掃除しやすくなるのでおすすめです。
万が一カビが発生しても早めに発見できるので、ひどくなる前に対処できます。
- 取り出すのが大変な収納はNG
- 湿気が溜まりやすい下や四隅には、布団を収納しない
- 壁から5~10cm程度離して収納する
- 外壁に面した部分は結露しやすいため、より多めに隙間を空ける
- 布団の下に「すのこ」を置く
対処法③こまめに掃除する
定期的に掃除をして、カビの栄養となる皮脂汚れ・ほこり・食べこぼしなどを除去しましょう。
ほこりは湿気を吸収しやすいので、湿気対策にもなります。
押入れに収納しているものを出すタイミングで、掃除機でほこりを吸い取りましょう。
壁面や床の状態をチェックすれば、押入れの変色・異臭・湿っぽさなどの変化にいち早く気づけます。
押入れを掃除したあとはしっかり乾燥させ、湿気が溜まらないようにしましょう。
対処法④十分に乾かしてから収納する
使用したあとの服や布団は、湿気を多く含んでいます。
すぐにしまわず、乾燥させてから収納しましょう。
人間は季節に関係なく、睡眠中におよそコップ1杯分(約200ml)の汗を分泌するとされています。
濡れた衣類や布団を押入れに収納すると、密閉された狭い空間では湿度が上昇。
カビが繁殖しやすい湿度60%以上の環境を作り出してしまうのです。
使用したあとの布団や服は、すぐに押入れにしまわず風通しのよい場所で乾燥させましょう。
触って湿り気がないことを確認してから収納するのがおすすめです。
対処法⑤炭八を置く

押入れの湿度を調整するには「炭八」がおすすめ!
押入れのような湿気がこもりやすい空間には、この高い調湿力が大切です。
広葉樹でなく針葉樹を用いた炭八の調湿力は、備長炭の二倍以上!
消臭効果もあるので、押入れ特有のこもった臭いも解消できます。
市販の除湿剤のように使い捨てではなく、1ヶ月に1回ほど炭八を天日干しすれば、半永久的に使用できるのも嬉しいポイント。
炭しか使っていないので、お子さまやペットがいるご家庭でも安心です。
炭八を布団の間に設置すると、蓄積された湿気を取り除き、本来のふかふかした状態を維持できます。炭八を布団から少し突き出すように配置するのがポイント。
湿気の逃げ道を作り、効率的な調湿効果を実現しますよ。
押入れ専用に設計され、使いやすいサイズの「炭八押入用」をぜひお試しください。

押入れのカビについてよくある質問

ここからは、押入れのカビについてよくある質問と回答をまとめました。
押入れのカビのにおいを取りたい!
押入れにカビが発生すると、こもったような、湿った土のようなにおいが発生するケースがあります。
押入れのにおいを消すには、以下の方法がおすすめです。
- クエン酸スプレーで押入れ全体を拭く
- エタノールで押入れ全体を拭く
- 重曹を置く
- 炭八を置く
炭八は消臭効果も期待できます。
炭八を入れたあとの臭気レベルが10分の1に減少したという実験結果も。
押し入れだけでなく、下駄箱・食器棚・バッグなどにも使える炭八を、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
押入れの中のものもカビてしまった。どうすればいい?
押し入れにカビがひどくなっていると、収納していたものにもカビが広がっていることがあります。
グラニーレではさまざまなカビ対策・対処法をご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
布団にカビが生えてしまったらどうする?対処法と再発防止のポイント
服がカビ臭い?!服のカビ臭さを除去する方法やカビ予防におすすめのアイテムを紹介!
カバンがカビ臭い!カバンに発生したカビの除去方法やカバンのカビを予防する方法を紹介!
押入れに新聞紙って効果あるの?
新聞紙の表面は普通の紙よりボコボコしており、水分を吸収するため、湿度を吸収する性質があります。
- 押入れ全体に新聞紙を敷く
- 新聞紙を丸めて広げれば、表面積が増えより効果的
- 新聞紙が湿ってふやけてきたら、すぐに新しいものに交換する
ただし、梅雨など湿度の高い季節に新聞紙だけでは十分な除湿効果は得られません。
換気をする・除湿機を活用する・炭八を取り入れるなどほかの対策と組み合わせて効果が発揮されます。
カビがひどい押入れは、安全に除去して二度と生やさない対策を!

押入れに発生したカビの種類によって、適した掃除方法があります。
| カビの種類 | 白カビ | 黒カビ | 緑カビ |
| 特徴 | ・白色 ・ふわふわで綿のような見た目 ・アレルギーの原因になることも | ・黒色 ・ポツポツした見た目 ・木材などに根を張り奥まで入り込む | ・木材に発生しやすい ・木材を腐らせる |
| 発生条件 | ・湿度60~80% ・温度20~30℃ | ・湿度70%以上 ・温度25~30℃ | ・湿度60%以上 ・温度25~35℃ |
| 落としやすさ | 〇 | ✕ | △ |
| 対処法 | エタノール | 次亜塩素酸・塩素系漂白剤 | 次亜塩素酸・塩素系漂白剤 |
押入れのカビを掃除するときは、作業を安全で効果的に進めるために、以下の準備を行いましょう。
- 押入れの中に入っているものをすべて取り出す
- 窓や扉を開けて空気の通り道を確保する
- マスクを着用してカビの胞子を吸い込まないようにする
エタノールでカビを取る手順
1.ゴム手袋を装着する
2.濡らして固く絞った雑巾で、ほこりなどを取り除く
3.消毒用エタノールを吹きかける。カビが発生していない場所にも押入れ全体的に吹きかける
4.十分に乾燥させる
次亜塩素酸水で除去する手順
1.ゴム手袋を装着する
2.濡らして固く絞った雑巾で、ほこりなどを取り除く
3.次亜塩素酸水を吹きかける。カビが発生していない場所にも押入れ全体的に吹きかける
4.黒カビが落ちるまで放置する
5.固く絞った雑巾で拭く
6.十分に乾燥させる
塩素系漂白剤で除去する手順
1.保護のためゴム手袋やメガネ・ゴーグルを装着する
2.キッチンペーパーに塩素系漂白剤を含ませる
3.カビが気になる部分に塩素系漂白剤を含ませたペーパーを置き、ラップで覆う
4.10分ほど放置する
5.貼り付けたキッチンペーパーをはがす
6.水を含ませたキッチンペーパーで塩素系漂白剤をしっかり拭き取る
7.十分に乾燥させる
押入れのカビが悪化する前に、次の方法で予防・対策を行い、清潔で快適な収納環境を保ちましょう。
- 押入れの空気を入れ替える
- 押入れの収納に余白を作る
- こまめに掃除する
- 十分に乾かしてから収納する
- 炭八を置く
著者情報

最新の投稿
 カビ2026年2月17日炭八の除湿効果は本当?口コミで分かったリアルな実力と使い方
カビ2026年2月17日炭八の除湿効果は本当?口コミで分かったリアルな実力と使い方 炭八2026年1月20日炭八は天日干しが必要?月1回の天日干しで半永久的に使える正しいお手入れ方法
炭八2026年1月20日炭八は天日干しが必要?月1回の天日干しで半永久的に使える正しいお手入れ方法 炭八2025年12月18日【炭八の量】何個置けばいい?場所別の使用量・サイズ・失敗しない選び方
炭八2025年12月18日【炭八の量】何個置けばいい?場所別の使用量・サイズ・失敗しない選び方 炭八2025年11月20日炭八のカバーは代用できる!おすすめ代用品6選と失敗しない選び方
炭八2025年11月20日炭八のカバーは代用できる!おすすめ代用品6選と失敗しない選び方








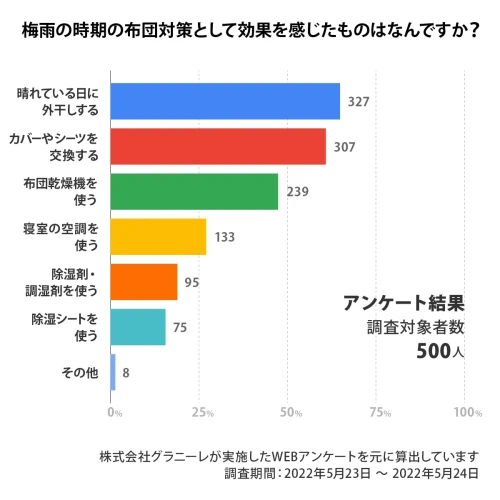

この記事へのコメントはありません。