

家全体がカビ臭い原因は?部屋別の対処法を詳しく解説
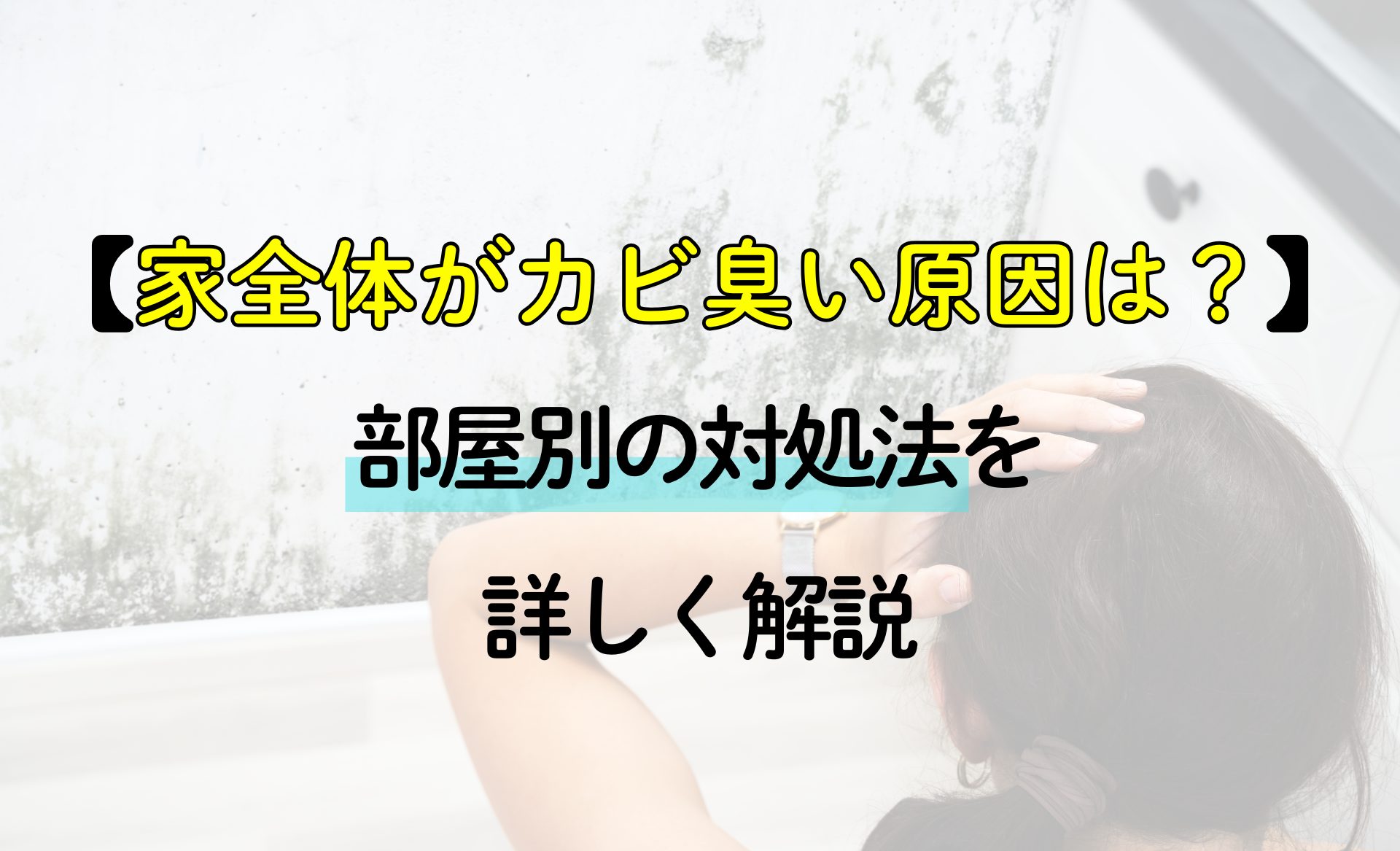
「最近、家に帰るとカビ臭さが気になる…」そんな悩みを抱えていませんか?
家全体にカビのようなニオイが広がっている場合、床下や壁、水回りなどにカビが発生している可能性があります。
カビ臭さを放置すれば、健康被害や建物の劣化に繋がるため早めに対処しましょう。
この記事では家全体がカビ臭い原因について詳しく解説します。部屋別の対処法も紹介するので、カビ臭に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

家全体がカビ臭くなるのはなぜ?

カビは湿気と栄養がある場所で繁殖し、栄養を分解・吸収する過程で老廃物を出します。
この老廃物が家全体に広がることで、部屋中がカビ臭くなる原因に。
カビが見えないのに臭いがする場合は、ソファーやベッド、屋根裏、家具の後ろなど見えない場所に生えていることもあります。
家の中を細かく探してカビの発生源を特定しておきましょう。
カビの種類や特徴については「私たちにとって身近なカビの種類と特徴について解説」で解説しているため、参考にしてみてください。
家全体がカビ臭い3つの原因

家全体がカビ臭い原因は以下になります。
- 換気ができない
- 除湿対策をしていない
- 家自体が劣化している
それぞれ詳しく解説します。
①換気ができていない
換気が不十分だと湿気やカビ胞子がこもってカビが発生しやすくなります。
特にクローゼット・押し入れ・収納の奥など風通しの悪い場所はカビの温床になりやすく、そこからカビ臭が広がりやすいです。
また、換気扇を掃除していないと空気を十分に吸い込めないため、湿気がたまりやすい傾向に。換気扇などはカビ対策としてこまめなお手入れを心がけましょう。
換気については「最適な換気回数は?換気に必要な時間や換気のメリットを紹介!」で解説しているため、参考にしてみてください。
②除湿対策をしていない
カビは湿度60~70%以上で活発に繁殖します。除湿対策をしないと、目に見えない場所(壁の裏、床下、家具の裏)でもカビが繁殖し臭う原因となります。
特に梅雨や夏場、または加湿器を多用する冬場にも湿気がたまりやすくなり、カビの温床になりかねません。
洗濯物の室内干しや結露など、日常生活で発生する水分もカビの原因となるため生活の見直しも必要です。
家全体の湿度管理ができていないと、壁や建材を通じて家全体にカビが広がるため早めに対策しておきましょう。
③家自体が劣化している
古い家は建材や断熱材の劣化によりカビが発生しやすい傾向があります。
雨漏りや結露、断熱性の不足、換気設備の老朽化などもカビの原因となるため、注意が必要です。
特に、長期間空き家だった住宅では、換気や清掃が行き届かず、ホコリや汚れがたまりやすい傾向に。入居前にはしっかりとクリーニングを行い、カビの発生源を除去しておきましょう。
断熱材や木材の内部までカビが入り込んでいる場合は、表面を掃除してもニオイが取れないことがあります。その場合は、リフォームを検討し安心して暮らせるように家を整えておきましょう。
家がカビ臭い原因となりやすい場所と対処法

家がカビ臭い原因になりやすい場所は以下です。
- エアコンの中
- 浴槽のエプロン
- 排水口
- トイレのタンク
- 押入れの奥
- 床下
- 壁紙の裏
対処法と合わせて紹介していきます。
エアコンの中
エアコンは室内の空気を吸い込み、冷やした空気を部屋に送ります。
空気を取り込むときに室内のホコリも一緒に吸い込むため、汚れが内部にたまりカビ臭い原因となります。
エアコンの中でカビが発生すると、涼しい空気と一緒にカビの胞子を部屋に飛ばしてしまうため早めに対策をしましょう。
エアコンのカビを除去する掃除方法は以下になります。
- エアコンの外側を掃除する:エアコンのボディについているホコリを除去する
- エアコンのフィルターを掃除する:フィルターを取り外し外側から掃除機でホコリを吸い取る、ホコリをとり終えたら水洗いをして、日陰に干して完全に乾いてから戻す
- 吹き出し口を掃除する:エアコンの吹き出し口とルーバー(風向きを変える羽)についているホコリを拭き取る
部屋全体の空気を清潔に保つためにも、定期的にエアコンを掃除しましょう。
浴槽のエプロン
浴槽のエプロンとはお風呂の側面についているフタの部分です。
浴槽エプロンは掃除がしにくく、湿気がこもりやすいためカビが発生しやすい場所。特に20〜35℃前後の高温多湿なお風呂はカビにとって最適な環境といえます。
カビの栄養となる皮脂・汗・石鹸や雑菌も多いため、こまめに掃除をしましょう。
エプロンの外し方はメーカーによって異なります。無理に取り外そうとすると故障の原因になるため、必ず手順を確認しましょう。
浴槽エプロンを掃除するときは以下の流れがおすすめです。
- 浴室用の中性洗剤、柄の長いブラシ、スポンジ、雑巾、キッチンペーパー、ゴム手袋、ゴーグルを準備する
- 説明書に従ってエプロンを外す
- シャワーでエプロンを50〜60℃のお湯で洗い流す
- 大きな汚れはキッチンペーパーで取り除く
- 洗剤を使ってスポンジでカビをこする
- エプロンを乾燥させたら装着する
エプロン掃除は年2回の掃除がベストです。特に夏前はカビが生えやすいため春と、夏が終わり涼しくなる秋に行うとよいでしょう。
お風呂のニオイについては「お風呂から嫌な臭いが?!お風呂が臭い原因や対策方法を紹介!」で紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
排水口

排水口からカビのにおいがする原因は以下の4つになります。
- 排水トラップの中の水がなくなる
- 排水ホースや塩ビ管が破裂している
- 排水管そのものが汚れている
- 排水口が汚れている
排水トラップとは排水管の途中に設置され、水を溜めることで下水の臭いや害虫・ガスなどが屋内に侵入するのを防ぐための構造です。
水でフタをすることで下水のにおいを防いでいますが、水がなくなることで部屋が臭くなってしまうことも。排水トラップを確認し、水がなければ適量注いでおきましょう。
排水ホースが破裂するとにおいだけでなく、水漏れの原因となってしまうため早めの対処が必要です。ホームセンターで同じホースを購入することもできますが、業者に依頼し安全に行うのが無難でしょう。
排水口や排水管が石鹸や食べカスで汚れているとカビが繁殖し、部屋ににおいがこもるようになります。
排水管が汚れている場合はパイプクリーナーなどの洗剤を使用して落としましょう。
排水口は重曹とお酢で掃除ができます。重曹2カップを排水口にまんべんなくなじませ、お酢1カップをかけ、1時間ほど放置します。放置した後に60度程のお湯で流せばカビを処理できるため試してみましょう。
トイレのタンク

トイレのタンクは水回りであるため湿気が多く、掃除する回数も少ないためカビの原因になりやすいです。
トイレタンクのカビは中性洗剤を使って落とす以下の方法がおすすめです。
- キッチン泡ハイター、ウタマロクリーナー、使い捨てのブラシやタオルを準備する
- トイレの手洗い場の水垢をとる
- 水が流れないように栓を止め、ウタマロクリーナーをタンクに入れてトイレタンク内のカビを取る
- 全ての水を洗い流し、細かい汚れをウタマロを吹きかけてタオルで拭き取る
- タンクにトイレタンク用洗剤を入れて終了
トイレタンク用の洗剤にはアルカリ性成分が含まれており、防カビ対策に役立つためぜひ使ってみましょう。
押入れの奥
押し入れは湿気がこもりやすく、カビのエサとなるほこりも溜まりやすいため要注意です。
特に梅雨や冬の結露が発生しやすい時期はカビ対策が必要になります。
押し入れの奥のカビは消毒用エタノールで以下のように対処しましょう。
- 押し入れから収納物を取り出してほこりなどを取る
- 消毒用エタノールを雑巾に染みこませ、気になる箇所を拭く
- 拭いた箇所が乾いたら収納物を片付ける
消毒用エタノールがない場合は、クエン酸スプレーや酸素系漂白剤も代用できます。ただし、クエン酸スプレーは殺菌力がないため、再発は防げないことは覚えておきましょう。
消毒用エタノールで落ちない黒カビは「塩素系漂白剤」が効果的です。壁紙の色が抜けたり、木の表面が痛む可能性があるため、狭い範囲でまず確認してから使用しましょう。
押し入れのカビについては「押し入れがカビ臭い原因は? 除去方法と自分でできる対策を紹介」で解説しているため、参考にしてみてください。
床下
床下は湿気がこもりやすいため、カビが発生しやすい場所です。床下にカビが生えると部屋までにおう原因となるため、早めに対処しましょう。
床下のカビを防ぐポイントは以下の3つです。
- 床下換気口をふさがない
- 床下に調湿剤を置く
- 床下に換気扇を設置する
床下には基礎部分に作られた換気口があります。物を置くなどして塞いでしまうと空気の流れが悪くなり、カビの繁殖原因となってしまうため防いでいないか確認しましょう。
換気対策には調湿剤、換気扇を設置するなどの方法もあります。湿気だけでなく悪臭予防にもなるため、カビ以外のにおいにも困っている家は検討してみましょう。
床下のカビについては「床下からの嫌な臭いは危険信号!床下のカビ放置は厳禁。大切な家を守るために湿気対策を」で紹介しているため、参考にしてみてください。
壁紙の裏

壁紙の裏は結露が発生しやすいため、カビが発生しやすい場所の1つです。カーテンや壁などで壁を塞ぐと空気の流れが悪くなり、カビが発生する原因になります。
壁にカビが生えたときの対処法は以下の通りであるため試してみましょう。
| ①壁紙を剥がして確認する | 目に見えない場所にもカビが広がっている可能性があるため、一部の壁紙を剥がして内部を確認する |
| ②カビ取り剤で除去する | アルコール(消毒用エタノール)やカビ取り専用スプレーを使ってカビを拭きとる |
石膏ボードまでカビが広がっている場合は、壁自体を取り替える必要があるためリフォーム業者に相談しましょう。
壁のカビは家の劣化にも繋がるため、発見したら早めの対処が必要です。
部屋のカビについては「部屋がカビだらけでも大丈夫!自分でできるカビ取りと二度と生やさない対策」で解説しているため、参考にしてみてください。
カビ臭い家は健康にも影響が出ることも

カビ臭い家に住み続けていると健康にも影響が出ることも。カビはアレルギー物質を放出しているため、アレルギー反応や炎症の原因になることがあります。
また、カビの胞子は肺に入ることで呼吸器系にも悪影響になることも。長期間カビを吸い続けると、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器疾患のリスクを高める原因になりかねません。
カビの仲間である真菌が肺に入って感染すると肺真菌症の原因となり、発熱・胸痛・咳・倦怠感などの症状が出現することも。
カビは健康状態にも悪影響が出るため、においを感じたら早めに対処しておきましょう。
参考:肺真菌症ってどんな病気?
カビ臭の予防には除湿が大切

カビ臭の予防には除湿が欠かせません。
カビは湿度が高い環境で繁殖しやすく、特に湿度が70%を超えると一気に増えます。
カビが見えなくてもにおいとして感じられることが多く、特に梅雨時期や夏の終わり、冬場の結露が発生する時期などは注意が必要です。
湿度を50%前後に保つことができればカビは繁殖しにくくなるため、除湿対策を心がけておきましょう。
除湿におすすめなのは炭八です。炭八は除湿や消臭効果もあるため快適な空間にしたい人にピッタリの除湿できる炭です。
天日干しで除湿効果が回復するため、除湿剤のように何度も買う必要がなくコスパを抑えてカビ対策したい人にぴったり。
見た目もおしゃれなので、お部屋のインテリアとしても楽しむことができます。家のカビ臭で悩んでいる人は炭八での除湿対策を検討してみましょう。
除湿方法については「ジメジメした湿気をなくす除湿方法6選!梅雨〜夏を快適に乗り切ろう」で解説しているため、参考にしてみてください。

家全体がカビ臭いときのよくある質問

家全体がカビ臭いときのよくある質問を集めてみました。
- 空気清浄機はカビ臭さを取ることができる?
- 部屋全体がカビ臭いときはどこが原因?
- 古い家のカビ対策は?
それぞれ詳しく紹介します。
空気清浄機はカビ臭さを取ることができる?
空気清浄機はカビ対策に有効です。空気清浄機はカビの栄養源となる空気中の物質を取り除くことができるため、カビの繁殖を抑える効果があります。
空気清浄機を使って効率よくカビ対策するには、エアコンと併用して使う方法がおすすめ。
エアコンと一緒に使うことで空気の循環がよくなり、室内の空気をよりきれいに保ちやすくなります。
さらに、空気清浄機は風通しのよい場所に設置することで、空気の流れに乗ってより効果的に空気を清浄できるため試してみましょう。
部屋全体がカビ臭いときはどこが原因?
部屋全体がカビ臭いときは以下の場所が原因のことが多いです。
- エアコンの内部:エアコンをつけると内部のカビが部屋全体に広がる
- 押し入れ・クローゼット:湿気がこもりやすく入れている服や布団からにおう
- 壁や天井の裏側:結露によってカビが広がっている可能性がある
- 家具や家電の裏:空気の流れが悪く湿気が溜まりやすいためカビが生えている可能性がある
においの発生源を探すには、「エアコンの使用直後に臭うかどうか」「クローゼットを開けた瞬間に臭いが強くなるか」などで手がかりをつかむのが効果的です。
部屋のカビ臭については「部屋がカビ臭い!カビ臭さの対策方法や部屋にカビが発生する原因を紹介!」で解説しているため、参考にしてみてください。
古い家のカビ対策は?

古い家のカビ対策は以下になります。
- 換気を行う
- 消臭剤を置く
- カビを除去する
- 畳や壁紙を交換する
特に畳の裏や床下・エアコン・押入れの中・浴室・浴槽はカビが発生しやすいため、場合によってはリフォームを検討しましょう。
古い家のカビ臭については「古い家がカビ臭い?!カビの臭い対策やおすすめのアイテムを紹介!」で解説しているため、参考にしてみてください。
家全体がカビ臭いときのまとめ

家全体にカビ臭が広がる原因は、換気不足や湿気、建物の劣化などさまざまです。見えない場所でカビが繁殖しているケースも多く、気づかないうちに健康被害へとつながるリスクも。
カビ臭を根本から解消するには、原因を特定し、部屋ごとに適切な対処をすることが大切です。
また、普段から除湿や換気、清掃を心がけることで、カビの発生を防ぎ、においのない清潔な空間を保ちましょう。
除湿には炭八がおすすめです。
炭八は半永久的に使える自然素材の調湿アイテムで、除湿・脱臭・防カビの効果が期待できます。天日干しすれば効果が回復し、何度も使えるためコスパよく除湿したい人におすすめ。
見た目もおしゃれなので、インテリアとしても馴染みやすいため、おしゃれに除湿したい人にもぴったりです。
カビ臭に悩まされない快適な空間を手に入れたい方は、まずは炭八を検討してみましょう。

著者情報

最新の投稿
 炭八2026年1月20日炭八は天日干しが必要?月1回の天日干しで半永久的に使える正しいお手入れ方法
炭八2026年1月20日炭八は天日干しが必要?月1回の天日干しで半永久的に使える正しいお手入れ方法 炭八2025年12月18日【炭八の量】何個置けばいい?場所別の使用量・サイズ・失敗しない選び方
炭八2025年12月18日【炭八の量】何個置けばいい?場所別の使用量・サイズ・失敗しない選び方 炭八2025年11月20日炭八のカバーは代用できる!おすすめ代用品6選と失敗しない選び方
炭八2025年11月20日炭八のカバーは代用できる!おすすめ代用品6選と失敗しない選び方 炭八2025年10月15日炭八のサイズ選びで迷ったら|場所別おすすめサイズと失敗しない選び方
炭八2025年10月15日炭八のサイズ選びで迷ったら|場所別おすすめサイズと失敗しない選び方





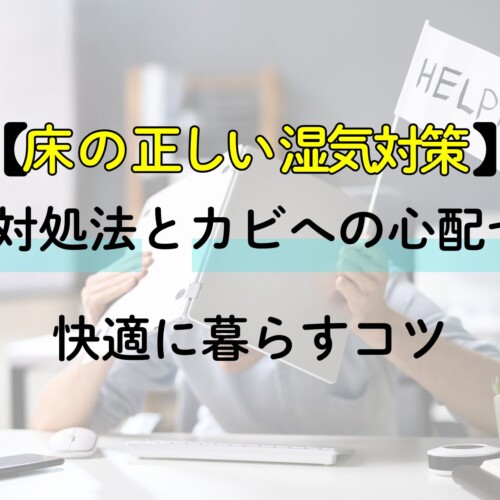
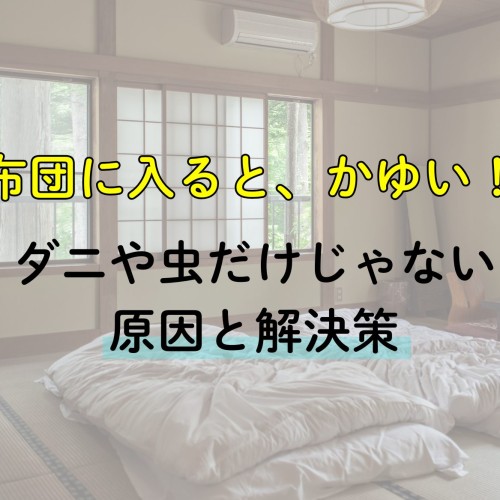

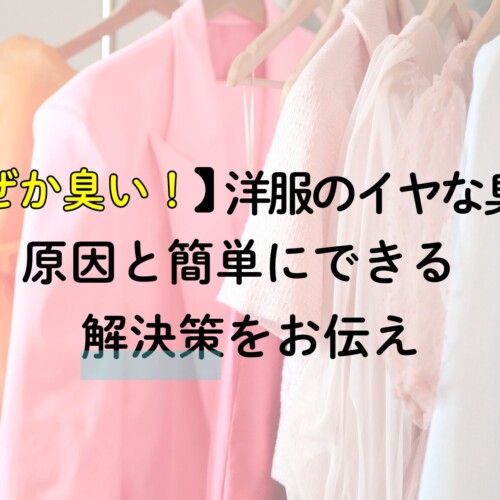

この記事へのコメントはありません。