

除湿のときに窓を開けてもいい?効率的な除湿方法とNGな換気方法を紹介
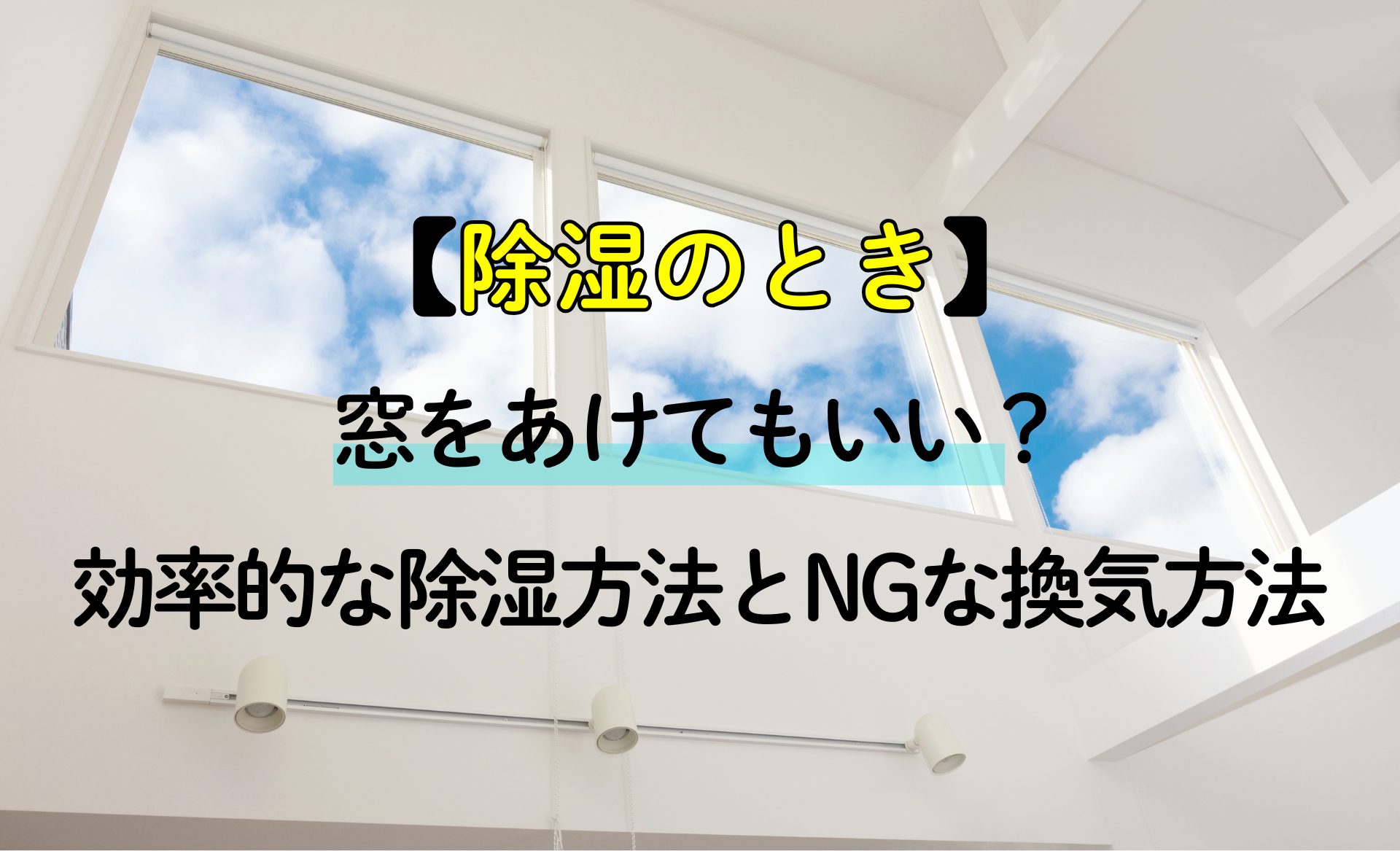
「湿気が多いけど、窓を開けたほうがいいの?」
「エアコンの除湿機能や除湿機を使いながら窓を開けて換気してもいい?」
「エアコンだけじゃなく、もっと効率の良い方法が知りたい」
このように、湿気対策をしようと思っても、窓を開けるべきか閉めて除湿をすべきか、正解がわからずに迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
特に雨の日や梅雨時期は、室内の空気がジメジメして不快なだけでなく、放っておくとカビの原因にもなってしまいます。
だからといって、除湿機やエアコンに頼ると電気代も気になりますよね。
また、電化製品だけに頼って除湿を行っても、新鮮な外気が入ってこないため、室内がどんよりすることもあるでしょう。
そこで今回は、正しい除湿や換気方法について、以下の点をお伝えします。
- 除湿をしながら窓を開けてはいけない理由
- エアコン除湿の正しい使い方
- 除湿機の正しい使い方
- 窓換気での除湿がおすすめなケース
- 除湿のために窓を開けると逆効果になるケース
- 日常に取り入れたい除湿対策
正しい除湿方法を知って、快適な生活空間を叶えていきましょう。
結論、除湿をしながら窓を開けるのはNG
エアコンや除湿機を用いて除湿をしているときは、窓を開けないようにしましょう。
なぜなら、外の湿気が室内に入り込んでしまうと、除湿効果が薄れてしまうからです。
エアコンの除湿機能や除湿機が効果を発揮するのは、密閉された空間の湿度を下げるとき。
窓を開けて空気が絶えず入れ替わると、外気中の湿気が室内に入ってきてしまいます。
特に梅雨や雨の日は、外の湿度が80%以上になることも。
せっかく除湿をした空間に、また水分を多く含んだ空気を入れることになります。
つまり、窓を開けることで除湿効果が打ち消されてしまうのです。
エアコンの除湿機能や除湿機能を使うときは、窓を閉めておきましょう。
エアコン除湿の正しい使い方
エアコンの除湿機能を活用すれば、簡単に部屋の湿度を下げることができます。
しかし、正しい使い方を抑えていないと、密閉状態の部屋でも十分な効果が得られない場合があります。かえって不快感に繋がることも。
エアコンの除湿機能を使うときは、以下3つの点に注意しましょう。
- 蒸し暑さが気になるときに使う
- 設定温度は適正に設定する
- シーズンごとにフィルターを掃除する
【使い方1】蒸し暑さが気になるときに使う
エアコンの除湿機能は、蒸し暑さ対策に効果的です。
なぜなら、除湿機能は湿気の取り込みに特化した機能であり、空気中の水分を取り除き乾いた空気を室内に戻すことで、湿度を下げてくれるからです。
また、湿度は体感温度にも影響します。
温度はそれほど高くないのに、湿気で不快に感じるときは、除湿だけでも十分に涼しく感じられる場合が多いです。
【使い方2】設定温度は下げ過ぎない
実は、エアコンの除湿機能は、冷房よりも電気代がかかるケースがあります。
なぜなら、湿気を取るためにコンプレッサーが頻繁に作動するからです。
涼しくしたいと思って温度設定を下げすぎると、結果的に電気代が跳ね上がることも。
気温の高さが気になるときは冷房を使うようにしましょう。
そのうえで湿気も気になる場合は、冷房で室温が十分に下がってから除湿に切り替えてください。
【使い方3】シーズンごとにフィルターを掃除する
見落としがちですが、フィルターの汚れは冷却・除湿の効率を大きく下げます。
シーズンの変わり目には必ず掃除して、空気の通り道を確保しておきましょう。
また、フィルターが汚れているということは、ほこりやカビの胞子が溜まっているということ。
そのままエアコンを使うと、機械内からの風と一緒に、ほこりやカビの胞子が室内にばらまかれてしまいます。
不衛生なことはもちろんですが、アレルギーなどの健康に関わってくることもあります。
定期的に手入れをし、清潔な状態で使いましょう。
除湿機の正しい使い方
除湿機は、特定の部屋や空間の湿気を集中的に取ってくれる頼もしいアイテムです。
ただし、きちんと効果を得るためには正しい製品の選び方や使い方を知っておくことが大切。
除湿機を使った湿気予防を検討中の方は、次の3点に注意してください。
- 性能を確認したうえで購入する
- フィルターの手入れをする
- 湿気だけを下げたいときに使う
【使い方1】性能を確認したうえで購入する
一概に除湿機と言っても、部屋の広さによって選ぶ製品は異なります。
また、運転音の大きさやキャスターの有無も、製品によってさまざまです。
広い部屋で使いたい場合は、タンク容量が大きいものを選びましょう。
夜間や仕事スペースで使いたい方は、運転音が小さなものがおすすめ。
各部屋を移動させながら使いたい方はキャスターつきが便利です。
【使い方2】フィルターの手入れをする
エアコンと同様、除湿機もフィルターにほこりが溜まっていると効率が悪くなります。
また、水タンクの中身を毎回捨てても、多少の水滴が残ってしまうでしょう。
ほこりや水滴が残っていると、劣化やカビの発生につながります。
2週間~1か月に1度は、フィルターの掃除や水タンクの清掃を忘れずに行いましょう。
【使い方3】湿気だけを下げたいときに使う
除湿機には、エアコンの除湿機能のような室温を下げる効果はありません。
また、空気洗浄機のように花粉や黄砂などを除去する機能も持ち合わせていません。
除湿をしながら部屋を涼しくしたいときは、エアコンの除湿機能を使うか、冷房機能と除湿機を併用しましょう。
空気洗浄もしたいようであれば、除湿機能付きの空気洗浄機の購入がおすすめです。
窓換気での除湿がおすすめなケース
エアコンの除湿機能や除湿機よりも、窓換気で湿気対策を行ったほうがいいケースもあります。
具体的には、次の3つのケースです。
- 新鮮な空気を取り入れたとき
- 風呂場やトイレの換気をしたいとき
- 換気口が汚れているとき
【ケース1】新鮮な空気を取り入れたいとき
外の湿度が低い晴れた日には、窓を開けて換気を行いましょう。
エアコンや除湿機で湿度を下げられたとしても、空気がこもっていることには変わりありません。
生活臭をはじめとしたにおいもこもりやすくなります。
定期的に窓を開けて空気を入れ替えることで、快適な空気を取り込むようにしましょう。
【ケース2】風呂場やトイレの換気をしたいとき
浴室やトイレなどは、除湿機を設置しにくい場所。
特にトイレは、いやなにおいが漂ってしまう場合もあります。
そうした場所は、定期的に窓を開けて湿気とにおいを逃がすのが有効です。
お風呂場は換気扇を回すことも大切ですが、翌朝になっても水滴が残っているということもあるのではないでしょうか。こうした水滴が、カビのもとになってしまいます。
換気扇と窓換気を併用して、より効率的に空気を入れ替えるようにしましょう。
【ケース3】換気口が汚れているとき
特にマンションや集合住宅では、換気口が目詰まりしているケースもあります。
管理がきちんとされていない場合は、換気口からの空気と一緒に、ほこりが入ってきてしまう場合も。
この場合、換気口を使っても、むしろ室内が汚れてしまう場合があります。
換気口を使う頻度を抑えながら、窓換気で空気を入れ替えるようにしましょう。
除湿のために窓を開けると逆効果になるケース
除湿だけではなく、空気の入れ替えやにおい予防に効果的な窓換気。
しかし、窓換気をすることで室内の湿度が高くなったり、汚れが入ってきてしまうケースもあります。
次の3つのケースでは、できるだけ窓換気は避けるようにしましょう。
- 雨の日
- 花粉や黄砂が飛んでくる時期
- 大通り沿いに住んでいる場合
【ケース1】雨の日
雨の日は外気の湿度が非常に高く、80〜90%以上になることも珍しくありません。
そうした環境で窓を開けると、外の湿気が一気に室内に入り込んでしまい、室内がジメジメとしてしまいます。
エアコンの除湿機能や除湿器を併用する場合であっても、常に外気が出入りする状況では、効率が極端に悪くなってしまいます。
電気代が無駄にかかるだけでなく、室内の快適さも保てません。雨の日の除湿は、できるだけ窓を閉めて行うのが鉄則です。
【ケース2】花粉や黄砂が飛んでくる時期
春や秋になると、花粉や黄砂が多く飛散する季節になります。
こうした時期に窓を開けると、外気と一緒にアレルゲン物質も室内に入ってきてしまいます。
家具や布団などが汚れてしまうのはもちろんのこと、室内にいても、常に花粉などにさらされてしまうことに。
掃除の手間や健康被害を防ぐためにも、花粉や黄砂が気になる時期は除湿機や空気清浄機を併用しながら室内環境を整えるのがおすすめです。
【ケース3】大通り沿いに住んでいる場合
大通り沿いの住宅では、車の排気ガスやほこり、騒音といった問題がつきものです。
こうした環境で窓を開けて除湿しようとすると、湿気と一緒に空気の汚れも室内に取り込んでしまい、かえって空気環境が悪化する可能性があります。
排気ガスによるニオイや、細かい粉塵が部屋に入り込むと、健康面にも悪影響が出ることもあるため注意が必要です。
窓を開けずに除湿機を使用し、必要に応じて空気清浄機やサーキュレーターを併用するのがベストです。
日常に取り入れたい除湿対策
「電化製品に頼り過ぎたくないけど、窓も開けられない」
「エアコン除湿や除湿機は便利だけど、電気代がかさむから心配」
「フィルターの掃除や水タンクに溜まった水捨てが面倒くさい」
など、窓換気や電化製品を使っての除湿にお悩みの方も多いでしょう。
しかし、放っておくとカビや白アリの繁殖に繋がってしまうことも。
家の床材などが劣化してしまう原因にもなります。
次の3つの工夫を取り入れ、簡単に湿気対策を行いましょう。
- 扉や引き出しは定期的に開ける
- こまめに掃除する
- 湿気取り剤を使用する
【工夫1】扉や引き出しは定期的に開ける
クローゼットや押し入れなどの収納スペースは、空気がこもりやすく、湿気が溜まりやすい場所です。
特に布製品や木材がある場合は湿気を吸収しやすく、カビや臭いの原因になりがち。
1日1回、数分間でも扉や引き出しを開けて空気を循環させると、湿気やにおいがこもりにくくなります。
晴れた日や乾燥している時間帯を選ぶと、より効果的です。
窓換気を行っているときや掃除をする際などに、収納スペースも開けておくようにしましょう。
【工夫2】こまめに掃除をする
湿気対策には掃除も大切です。ほこりや汚れがたまった場所はカビの温床になりやすく、特に家具の裏や部屋の隅、換気が行き届かない箇所は注意が必要です。
こまめに掃除機をかけたり、雑巾で水拭き・乾拭きをすることで、ほこりの蓄積を防ぎ、カビの発生リスクを大幅に下げることができます。
湿度が高い日でも、室内を清潔に保っていれば、湿気による被害は起こりにくくなります。掃除は週に1〜2回を目安に、特に湿気が気になる季節は意識的に取り組みましょう。
【工夫3】湿気取り剤を使用する
あまり手間を掛けずに湿気対策をしたい方におすすめのアイテムが、湿気取り剤。
湿気が気になる場所に置いておき、あとは放置するだけで大丈夫なため、取り扱いが簡単です。
特に小型の湿気取り剤が多いため、クローゼットや押し入れ、靴箱など湿気がこもりやすい場所の湿気対策としておすすめ。
部屋全体用にクッション大の製品もあるので、梅雨や雨の日が続く時期には、こうしたグッズを併用することで湿度の上昇を防げます。
定期的に中身を交換するタイプが多いため、使用期限をチェックしながらこまめに取り替えるのがポイントです。
買い替えが手間だと感じる方は、半永久的に使用できる製品を選ぶといいでしょう。
窓を開けられないときでも除湿をするなら、炭八がおすすめ!
炭八は、針葉樹を原料としている湿気取り剤です。
吸湿力は備長炭の約2倍と言われており、半永久的に使用できます。
つまり、一度購入すれば、高い除湿効果を半永久的に期待できるということ。
除湿力を保つために必要なのは、定期的な天日干しのみです。
晴れた日にベランダに置いておくことで、内部に溜まった湿気を外に掃き出し、購入時同等の除湿力を取り戻します。
さらに、におい取りの効果もあります。
窓換気がなかなかできず生活臭が気になる方や、下駄箱などの湿気とにおいの両方がこもりやすい場所に使ってみてください。
まとめ
今回は、窓を開けての除湿について、以下の点をお伝えしました。
- 除湿をしながら窓を開けてはいけない理由
- エアコン除湿の正しい使い方
- 除湿機の正しい使い方
- 窓換気での除湿がおすすめなケース
- 除湿のために窓を開けると逆効果になるケース
- 日常に取り入れたい除湿対策
窓換気は、除湿だけではなくにおい対策にも効果的ですが、正しく行わないと、室内の湿度が高くなる場合や汚れを取り込んでしまう場合があります。
正しい湿気対策を知って室内環境を快適に保つための参考にしてください。
著者情報
最新の投稿
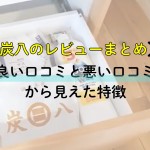 炭八2026年2月11日炭八のレビューまとめ|良い口コミと悪い口コミから見えた特徴
炭八2026年2月11日炭八のレビューまとめ|良い口コミと悪い口コミから見えた特徴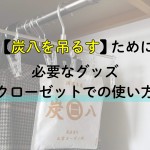 炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説
炭八2026年1月20日炭八を吊るすために必要なグッズ|クローゼットでの使い方を解説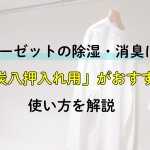 炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説
炭八2025年12月29日クローゼットの除湿・消臭には「炭八押入れ用」がおすすめ|使い方を解説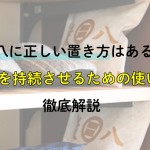 炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説
炭八2025年12月29日炭八に正しい置き方はある?効果を持続させるための使い方を徹底解説







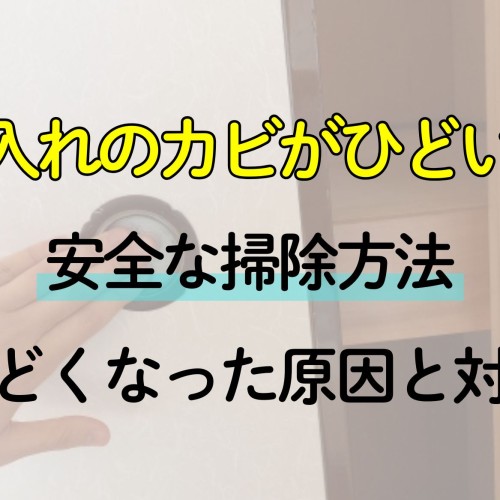



この記事へのコメントはありません。